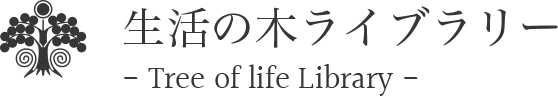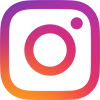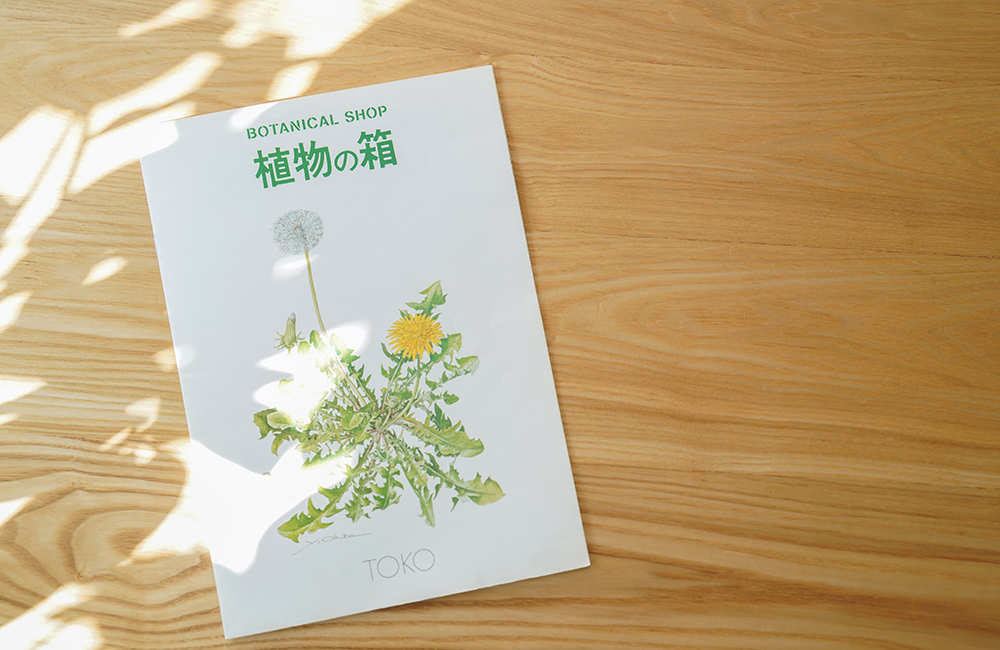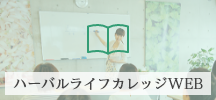檜(ひのき)の香りと言ったら檜風呂や新築の香りなど、香りの想像がつく方も多いのではないでしょうか。
日本人になじみのある檜の香りですが、その檜がどのように育てられ、どのように加工されて精油(エッセンシャルオイル)になるのでしょうか。
檜の産地、三重県の尾鷲を訪ねました。

森林の入り口に着くと、曇り空から次第に晴れ間が垣間見え、檜や杉の針葉樹が中心の森林に木漏れ日が差し込み始めました。
歩道に敷かれた檜チップも相まって、深呼吸をすると青々しい葉や木々の香りを存分に感じられます。
普段なかなか感じられない森林の香りに、取材しながらもついつい癒されました。

Hinoki
[ヒノキ]
学名:chamaecyparis obtusa
ヒノキ科
雪などの寒さにやや弱く、日本では比較的太平洋側の地域に分布する針葉樹。
英名では「Japanese cypress(ジャパニーズサイプレス)」の名でも知られています。
針葉樹特有の芳香成分のα-ピネンや酢酸ボルニル、特徴成分のカジノ―ル類を含み、深みのあるウッディ感だけでなく、爽やかなグリーン感もほのかに感じられる木の香りです。
尾鷲で檜を育てる
海沿いのこの地域は檜にとって厳しい生育環境となっており、他の地域に比べると成長速度が遅く、その分年輪の密度が高く強度がある他、油脂分が多い特徴があります。
樹齢100年を超える檜などもあちこちにありますが、生産者の方曰く、植えてしまえば動けない檜が快適に生きていくためのスペースづくりとして、「間伐」が檜の生育では特に重要で難しいそうです。

植え付け前の檜の苗木
春に植林をして、夏に間伐や下草の処理をし、秋冬に太い木を伐り始めます。
このような流れで1年を通し森林の生育を管理していくのですが、市場では立木の価格が近年低下していることもあり、森林運営の維持が年々難しくなっている現状があります。
難しくありつつある森林運営の中で、春に植えた檜はどのくらい育つと精油になるのでしょうか。
檜精油ができるまで

①材料の加工
生活の木の檜精油は、樹齢およそ80年ほどの建材にならない根元部分を材料にしています。
樹齢が80年のものになると、香りがさらに上質に感じられるそうです。
これらをさらに効率的に採油するためチップ状に加工します。



②蒸留窯に檜チップをいれる
人が平気で何人も入れるサイズの蒸留窯に1t以上の檜チップを入れていきます。
山盛りの檜チップの上に装置を取り付けたら蒸気を入れていきます。


③精油を抽出する
蒸気で檜チップを蒸留し、30分ほどたつと徐々に精油を含む芳香蒸留水が採れ始めます。
精油は蒸留水よりも比重が軽いため上部に浮く性質があり、下部の蒸留水を流し終えると精油が残ります。
抽出したての檜精油の香りもなんとも清らかな樹々の香りでした。
また、精油の抽出を終えた檜チップたちはその後捨てられるのではなく、バイオマス燃料として再利用されています。
檜の"木"は身近に感じますが、"精油"の採油率はおよそ1.2%とごくわずかでとても希少ということがわかります。
(檜チップ1tに対して採れる精油はおよそ12kg)
檜精油は、おうちに居ながら日本特有の落ち着きや、目を瞑ると森林浴をしているような感覚を楽しめると思います。
ぜひ、檜精油のもつ香りの奥ゆかさを感じてみてください。
Text by O.T.A.